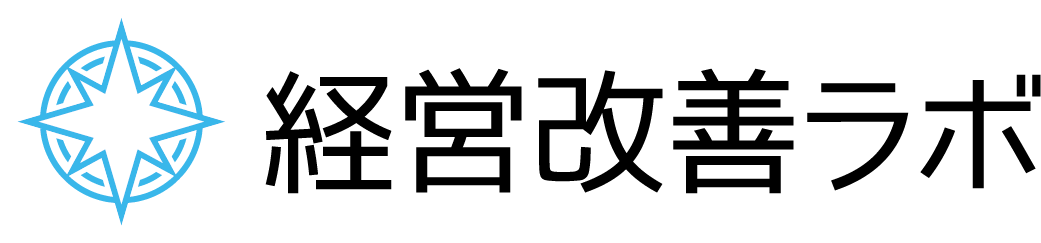設備投資を行うと償却年数に応じて取得費用を経費として計上できますが、特別償却とは、それとは別に、「特別に」減価償却することができる制度のことを言います。どのような場合に特別償却を行うことができるのか、会計処理なども併せて詳しく説明します。
1.特別償却とは

特別償却とは、序文で述べたように、通常の減価償却費とは別に、経費を追加計することができる制度のことです。課税対象となる利益から特別償却費を差し引くことができるので、結果として法人税を減税することが可能になります。
最初に基本的な「減価償却」について説明します。ある会社が1,000万円の販売システムを導入したとします。この場合には会社の無形固定資産として「ソフトウェア」という勘定科目に1,000万円が計上されることになります。
仮に初年度からこの販売システムを使い始めたとすると、この販売システムの法定耐用年数が5年なので(参考:国税庁ホームページ「No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm)、1,000万円÷5=200万円となり、毎年200万円の減価償却費の計上が可能となります。
通常はここまでで減価償却の計上は完了してしまうのですが、例えば、中小企業投資促進税制の対象となった会社では、30%の特別償却が認められています。つまり、上記の販売システムの例では、200万円に加えて、1,000万円×30%=300万円の特別償却が認められるので、初年度は200万円+300万円の500万円を減価償却費の計上が可能になります。
特別償却を実施するメリットは、設備投資を実施した翌年の税金を抑制することが可能になる点にあります。特別償却で節税を行うことで生じた余裕資金を、別の投資に振り向けることで、会社の資金を効率よく運用することが可能になります。
また、即時償却(設備などを購入して、即座に全額費用計上することが可能な償却方法)にはないメリットとして、特別償却は1年間の繰り越しをすることが可能な点があります。例えば、設備投資を実施したけれども初年度に特別償却をすると会社がと赤字になってしまうような場合には、特別償却(による減価償却費の計上)を翌年に繰り越すことができるようになっています。
即時償却の場合には、設備投資を実施するタイミングを多額の利益が見込める年に合わせなければなりませんでしたが、特別償却の場合は利益の多い年に実施する必要がありませんので、設備投資を行うタイミングの自由度は高いと言うことができるでしょう。
一方で、特別償却には以下のようなデメリットもあります。繰り越しをすることが可能な特別償却ではありますが、繰り越しを実施する場合には、税金の申告処理が少し複雑になります。特別償却費を翌年に繰り越した場合は、繰り越した金額は「特別償却不足額」という扱いになります。
この「特別償却不足額」は、法人税の申請を行う際に「別表」という用紙に記載する必要があるのですが、この手続きがやや煩雑であることには注意が必要です。
2.中小企業投資促進税制における特別償却

中小企業投資促進税制を例に特別償却の仕組みを説明します(出典:国税庁ホームページ「No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htmより)
|
中小企業投資促進税制 |
|
| 対象者 | ・中小企業者等*(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 |
| 対象事業 | 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、 卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、 一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、 旅行業、こん包業、郵便業、通信業、 損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、 不動産業、物品賃貸業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
| 適用要件 | 一定の対象設備の取得等をし、指定事業の用に供すること |
| 対象設備 | 機械及び装置:1台160万円以上 |
| ソフトウェア:1台70万円以上 | |
| 工具:1台30万円以上 かつ合計120万円以上 | |
| 普通貨物自動車:車両総重量3.5t以上 | |
| 内航船舶:取得価額の75%が対象 | |
| 措置内容 | ・特別償却率:30%
・税額控除:7% ※税額控除は個人事業主、資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る |
| 適用期限 | 令和6年度末まで |
*国税庁によると、中小企業者とは以下の説明に該当する法人を指します。
(出典:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm)
中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは対象から除かれます。
1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
(1) その発行済株式または出資(自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人
(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注2)に所有されている法人
(3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)
(注1) 通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。
(注2) 大規模法人とは、次の1から4に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
3 大法人(次の(1)から(3)に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
(2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(3) 受託法人
4 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記3に掲げる法人を除きます。)
3.特別償却に関する会計処理

特別償却を実施した場合には、通常の減価償却費に含めて、会計処理を行うことも可能です。しかし、特別償却の場合は、金額が巨額になってしまう可能性があるので、特別償却を適用した年度の減価償却費が他の年度と比べると多額となり、その年度の利益額が小さくなってしまうという状況が発生してしまいます。
その結果として、特別償却を実施した年度の自己資本比率(ROE)や総資産利益率(ROA)などの各種利益率等指標が低下してしまうという弊害が生じてしまいます。そのため、このような利益が少なくなってしまうという弊害が生じない方法として、準備金積立方式、という方法で会計処理することが可能になっています。
- 特別償却計上年度の決算時の会計処理(税効果会計は考慮せず)
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 繰越損益
減価償却費 |
500,000
1,000,000 |
特別償却準備金
減価償却累計額 |
500,000
1,000,000 |
特別償却準備金とは、資本の部の科目で、株主総会の承認がなくても積み立てが可能です。ただし、株主資本等変動計算書への記載が必要になります。
- 特別償却計上年度以降の会計処理
特別償却計上年度に計上した「特別償却準備金」を取り崩します。取り崩す期間は、耐用年数によって異なりますが、均等額を取り崩しすことになります。原則として、特別償却を行った設備の耐用年数が5年から9年の場合の取り崩し期間は5年、特別償却を行った設備の耐用年数が10年以上の場合の取り崩し期間は7年、となっています。
上記の会計処理の特別償却の対象資産の耐用年数を7年とすると、「5年から9年に」に該当するので、5年で取り崩すことになり、会計処理は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 特別償却準備金 | 100,000 | 繰越利益 | 100,000 |
まとめ

特別償却は節税手段としては有用な方法の一つではありますが、若干税金上の手続きが煩雑になります。しかし、手元資金の有用な使い道を検討することができるようになりますので、会社としてのメリットも大きな制度だと考えられます。