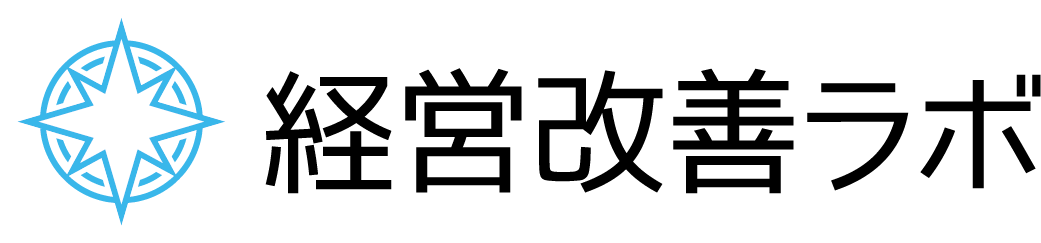常に利益を確保し続けることを会社経営の目標としている経営者は多いのではないでしょうか。
しかし残念ながら様々な要因で収益を確保することができなくなってしまう場合があり得ます。
当期に欠損金を発生させてしまった場合に、前年度に納付した法人税を還付してもらえる仕組みがあります。
これを「欠損金の繰戻還付」と言いますが、具体的にどのような仕組みになっているのでしょうか。
1.「欠損金の繰戻還付」の概要
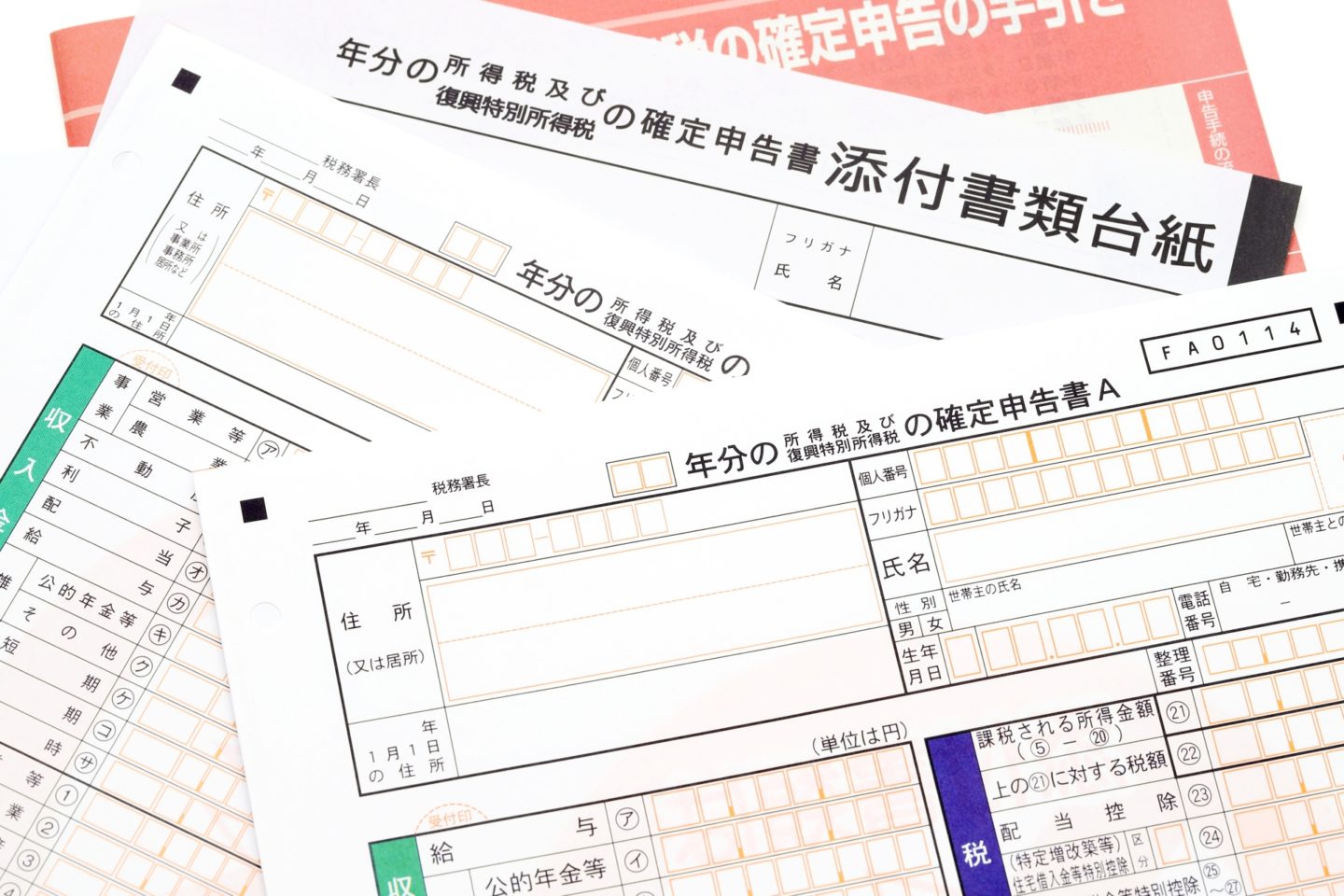
欠損金の繰戻還付とは、「欠損金額が生じた場合に、その欠損金額を事業年度開始前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して、納付した法人税額の還付請求をする事が出来る」(法人税法第80条)という制度のことです。
欠損金とは法人税において使用される用語で、会社の事業年度の損金合計額が益金合計額を上回っている状態のことです。
わかりやすく言うと「赤字」(所得金額がマイナス)のことを欠損金と言います。
この制度は、確定申告書(青色申告書)を提出する事業年度に欠損金額が発生した際に、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求することができる、という仕組みになっています。
この制度は、中小企業等のみが繰戻還付を受けることができる、ということになっています。
ここで言う「中小企業者等」とは、
・公益法人等又は協同組合等
・法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる法人(認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合)
・人格のない社団等
のような法人を言います。
なお、この制度は、中小企業者等以外の法人の平成4年4月1日から令和6年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用しないこととされていますが、中小企業者等以外の法人であっても、(1)清算中に終了する各事業年度の欠損金額、(2)解散等の事実が生じた場合の欠損金額、(3)災害損失欠損金額および(4)銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度を適用できることとされています。
(引用:国税庁「No.5763 欠損金の繰戻しによる還付」より)
ここで言う「解散等の事実」とは、解散、事業の全部の譲渡、会社更生法等による更生手続の開始など一定の事実のことを言います。(※適格合併による解散は対象外)
解散等の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度、もしくは解散等の事実が生じた日の属する事業年度において生じた欠損金額に対しては、「欠損金の繰戻還付」制度の適用が認められています。
また、災害損失欠損金額も繰戻還付を受けることができます。
災害損失欠損金額の繰戻還付は災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6か月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合に、その事業年度または中間期間(災害欠損事業年度)開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。
災害損失欠損金額とは、災害欠損事業年度の欠損金額のうち、災害損失の額(災害により棚卸資産、固定資産または一定の繰延資産について生じた損失の額で、資産の滅失等により生じた損失の額、被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額および被害の拡大または発生の防止のための費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除きます。)の合計額をいいます。)に達するまでの金額をいいます。
(引用:国税庁「No.5763 欠損金の繰戻しによる還付」より)
繰越欠損金については、「繰越欠損金ってなんですか?繰越欠損金の活用方法を紹介します」の記事でも詳しく解説しています。
2.「欠損金の繰戻還付」制度を利用できる法人の条件

(1)青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻しによる還付の場合
青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻還付を申請するには以下の3点を満たさなければなりません。
2.欠損事業年度の青色申告書(確定申告書)を提出期限までに提出していること
3.欠損事業年度の確定申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること
(2)解散等の事実が生じた事業年度の欠損金の繰戻しによる還付の場合
解散等の事実が生じた事業年度の欠損金の繰戻還付の申請には以下の2点を満たす必要があります。
2.解散等の事実が生じた日から1年以内に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること
(3)災害損失欠損金額の繰戻しによる還付の場合
災害損失欠損金額の繰戻還付の申請は以下3点を満たさなければいけません。
2.欠損事業年度の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出していること
3.上記(2)の確定申告書または仮決算による中間申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること
通常は(1)に該当する方が多いかと思います。
毎年提出期限に間に合うように確定申告を行うことが大切です。
3.欠損金の繰戻還付の還付額の計算方法
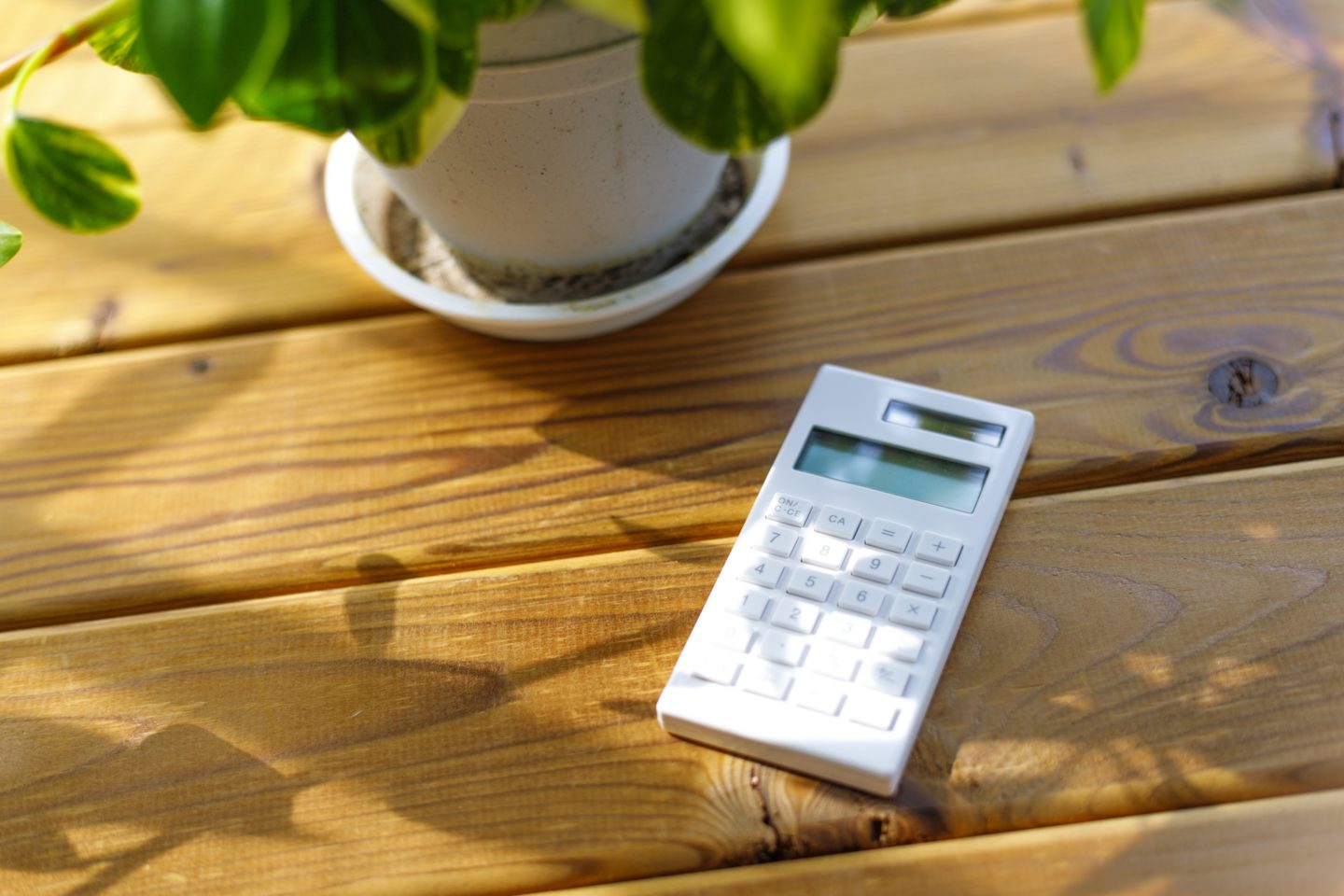
欠損金の繰戻還付における還付金額の計算は以下のとおりです。
例えば、前事業年度の所得が1,200万円、法人税額が180万円、当事業年度の欠損金額が600万円だった場合、還付請求出来る法人税の金額は180万円×600万円÷1,200万円=90万円、となります。
なお、還付所得事業年度の所得金額(分母の金額)、及び、会社が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額、が還付金額の限度となります。
4.欠損金の繰戻還付に関する仕訳

(1)還付請求をした事業年度の仕訳
| 貸方勘定科目 | 金額 | 借方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収還付法人税等 | XXX | 雑収入 | XXX |
なお、還付される金額は税金のため、消費税の課税対象外(不課税)となります。
(2)中間申告で中間納付額が有る場合の仕訳
① 仮払法人税等の金額を取り崩し、差額を雑収入等として計上
| 貸方勘定科目 | 金額 | 借方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収還付法人税等 | XXX | 仮払法人税等
雑収入 |
XXX
XXX |
差額は雑収入として計上されます。
② 翌事業年度に法人税が還付された時の仕訳
| 貸方勘定科目 | 金額 | 借方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現預金 | XXX | 未収還付法人税等 | XXX |
5. 地方法人税の還付

欠損金の繰戻還付は法人税法を対象とした制度です。
通常は還付請求をしても、地方税である法人住民税や法人事業税の還付を受けることはできません。
しかし、法人住民税については「控除対象還付法人税額」として、「地方税法第53条12項・第321条の8第12項」により、欠損金が発生した翌事業年度以降に「繰越控除」を受けることが可能になっています。
失念せずに、申告書(法人都道府県民税の場合は「第6号様式別表2の3」、法人市町村民税の場合は「第20号様式別表2の3」)に記載しましょう。
一方で、法人事業税には、上記の法人住民税のような「控除対象還付法人税額」の制度が存在していませんので、注意が必要です。
欠損金の繰戻還付まとめ
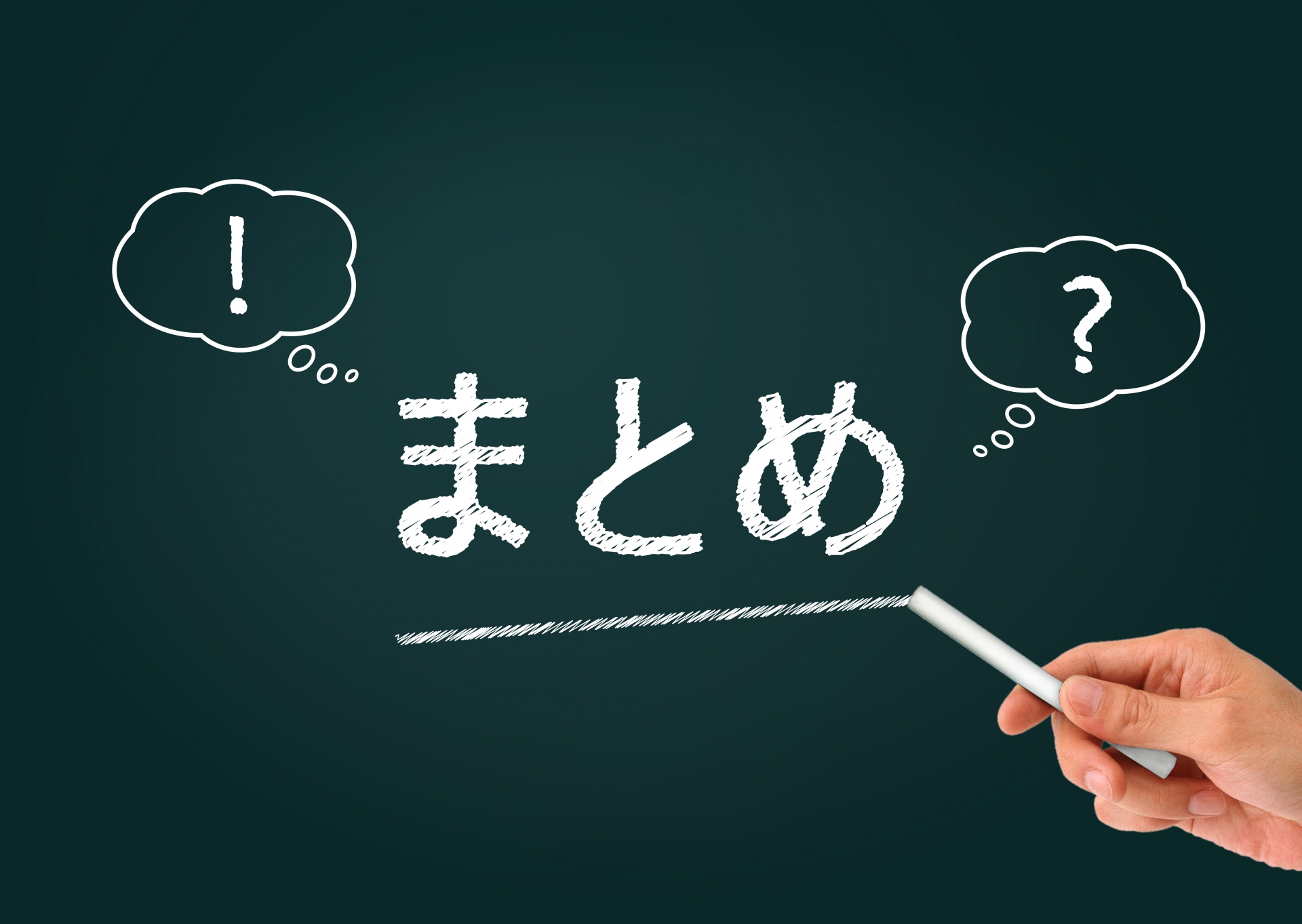
欠損金の繰戻還付は、過去の欠損金を有効に活用できる制度です。
活用のためにはいくつかの条件がありますが、予想外に会社の業績が悪化してしまった場合には、会社の経営を維持するためにも是非利用したい制度です。
中小企業に役立つ税制度に関しては、「中小企業投資促進税制とは?中小企業投資促進税制のメリットを解説」の記事でも紹介しています。