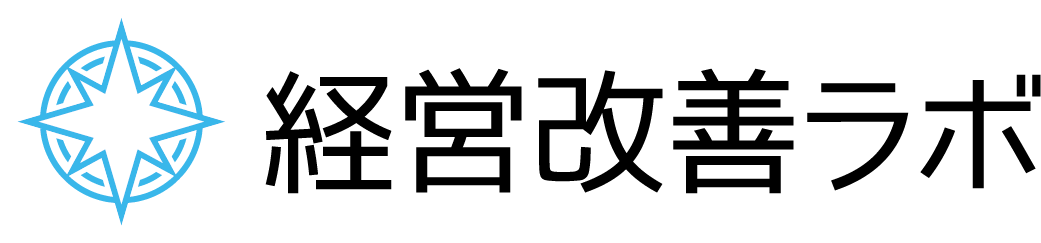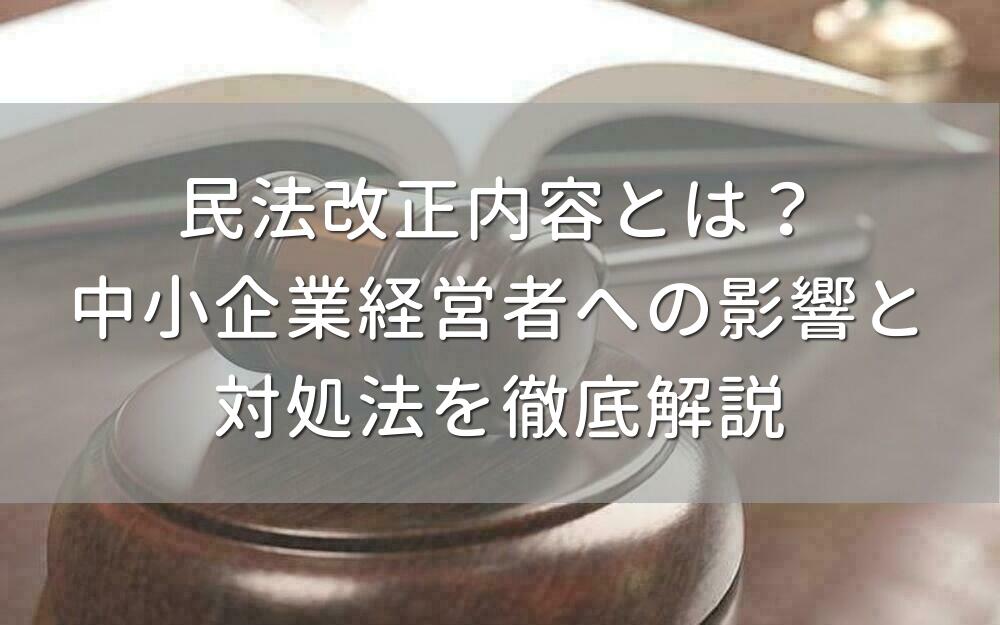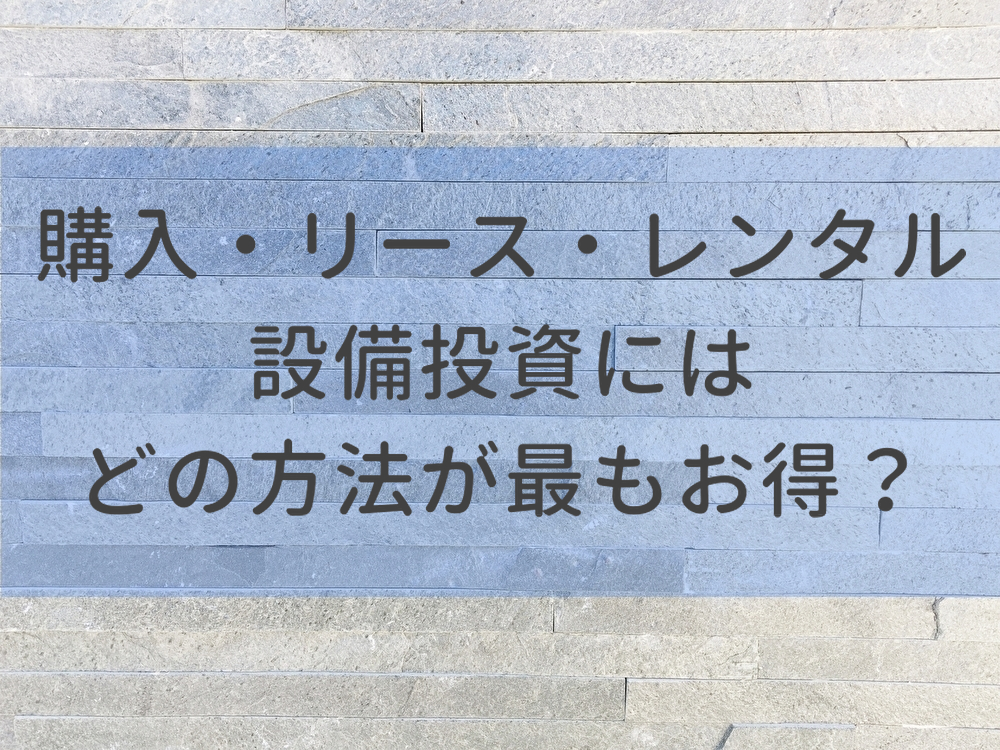1894年に民法が制定されてから2020年4月に約120年ぶりにようやく改正民法が施行されました。本稿では、民法が改正されることになった背景、改正民法の概要、中小企業を含む企業に与える影響とその対応方法、などについて詳しく解説します。
1.民法が改正されることになった背景
 改正前の民法は1894年(明治29年)に制定されて以降、条文のカタカナ書きをひらがな書きにあらためるといった変更は行われてきたものの、ほぼ最初に制定されたままの状態で120年以上が経過していました。
改正前の民法は1894年(明治29年)に制定されて以降、条文のカタカナ書きをひらがな書きにあらためるといった変更は行われてきたものの、ほぼ最初に制定されたままの状態で120年以上が経過していました。
それだけの時間の経過により、民法の内容が実際の国民生活に合わなくなっている部分が多く見受けられるようになってきました。民法は国民の生活に非常に密接している法律なので、このままでは民法が使いにくい法律となってしまうという心配が高まってきました。
そこで、国民生活の実態にマッチするように民法を改正しようという機運が盛り上がってきたのです。法務省では2006年から民法の全面改正の方針を打ち出しており、日本政府は2016年3月に最初に民法改正法案を国会に提出することになりました。
ところが、その時は他の重要法案の審議が優先されたため、民法改正法案の審議は見送られました。そして2016年秋から再び民法改正法案の審議が進められてきました。その後、2017年(平成29年)5月に民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
そして、2020年(令和2年)4月1日に新たな改正民法が施行されたのです。実に検討開始から14年もの月日をかけて、施行された改正民法とは、どのような点が大きく変更されたのか、また、それらの変更は企業経営にどういった影響を与える可能性があるのか、等に関して解説します。
2.企業活動に影響を与える民法改正の主な5つのポイント
<企業が理解しておくべき重要な民法の改正点>
| 改正点 | 概要 |
| (1)定型約款 | 不特定多数との取引で画一的な内容を定めている定型約款では、愛田形と契約内容に関して合意がなされたものされます。その一方で、信義則に反して一方的に相手方の利益を損なう内容は、定款約款の合意から除かれることになりました。 |
| (2)消滅時効 | 改正前の民法では、「権利を行使できる時から10年」を時効期間としていましたが、改正民法においては、債権者が「権利を行使できることを知った時から5年」、若しくは「権利を行使できる時から10年」、のどちらか早い方を、原則として、時効期間としています。この点は大きな変更ポイントであると考えられます。 |
| (3)法定利率 | 改正前の民法が定めていた法定利率は、年5%(なお、商取引における商事法定利率は年6%)にとされていました。改正後は、当初の法定利率を年3%と引き下げたうえで、その後3年ごとに利率を見直す、という変動制に変更されました。 |
| (4)保証債務 | 改正民法では、根保証(一定の取引関係から発生する、現在および未来の一切の不得意の債務を保証すること)で保証人が法人以外のもの(個人根保証契約)に関しては、保証の上限金額(極度額)を定める必要がある、とされました。 |
| (5)債権譲渡 | 譲渡の対象となる債権の本来の債務者と債権者の間において、債権譲渡の禁止や、または譲渡制限のをしたような場合(例えば、債権譲渡禁止特約をお互いに合意したケース)においては、譲渡禁止あるいは譲渡制限の効力が緩和されることになりました。 |
(1)定型約款
現代では、銀行と預金取引のような定型化されている取引を大量にこなケースにおいては、時間を節約して効率を上げて業務を行わなければなりません。そのために、多くのケースにおいて、ひとつひとつ個別事情を踏まえて契約内容を変更して契約を締結するようなことは皆無であり、ティピカル(定型的)な条項を定型約款に定めてるのです。
①民法改正で「定型約款」が検討対象になった理由
改正前民法では、約款に関して統一されたルールや決まりが定められていなかったので、例えば、インターネットを利用した通信販売や保険契約やといった取引を行う場合に多くのトラブルが発生していたのことは間違いのない事実でした。
これらの契約の約款は、事業側で前もって作成・用意されているものが大半であったため、消費者にとっては不利な契約内容や条項などが知らない内に盛り込まれやすい状態になっていることが従来から指摘されており、契約締結の前に約款をよく読んで注意するようにと注意されていました。
しかし、実際には契約の場面において、細かい文字がびっしりと記載された約款を法律にはけして明るくない一般人が隅から隅まで読んで理解することは至難の業である、ことも事実であったと言えるのです。
一方で、大量の取引を円滑に進めるためには約款そのものの存在は必要だとも考えられます。しかがって、余計なトラブルを発生させることなく、さらに約款の位置付けを明らかにするために「定型約款」に関しての明確なルール化の検討が行われてきたのです。
②今回の民法改正によってルール化された「定型約款」の要件
今回の民法改正においては、「定型約款」という概念が定めることになりました。定型約款とは、不特定多数の相手方に対して、定型的な取引を締結する際に、その契約の内容を補充することを目的として、契約当事者のどちらか一方があらかじめ準備した条項のことを指すことになりました。「定型約款」が適用されるためには、以下の2つの要件が整っている必要があります。
- 取引の内容の全部、あるいは一部が定型的であって、かつ契約当事者である両者にとって合理的な取引であること
- 契約の内容を補充することを目的として、当事者のどちらかが準備すること
③「定型約款」における合意の要件
本来は契約当事者同士がお互いに合意したものが契約となります。しかしながら、定型約款を使う取引においては、ひとつひとつの細かい個別の条項についてまで合意されることは非常に少ないものと思われます。
そこで、たとえ細かい個別条項に関して合意がなされていない場合でも、定型約款取引を締結することに合意した場合、あるいは定型約款の準備をした者が前もって定型約款を契約の内容とする旨を相手側に意思表示した場合、のどちらかの場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされることになりました。
<合意の要件>
-
- お互いに定型取引(銀行の預金取引など)を締結することの合意、双方とも定型約款を契約内容とすることに関する合意
または
- 前もって定型約款の契約の内容とする、という内容を相手方に表示
ただし、定型約款の条項の内容に、相手方が行使できる権利を制限したり、あるいは相手方に課す義務を重くするような内容で、その定型取引の状況や社会通念に照らし合わせて考えた場合に、著しく信義則に反していて相手側の利益を一方的に損ねる、と考えられるようなケースでは、定型約款に合意がなされなかった、とされることとなり、その条項は契約の対象にはなりません。
<定型約款が適用されないケース>
- 法外に高い違約金、などの不当な罰則条項が盛り込まれている
- 賠償額の金額が法外に低く抑制されている
- 社会通念上、信義則に反しており、一方的に相手側の利益を損なうと認められる
「定型約款」において、契約内容などの変更事由が発生した場合には、合理性があると認められるようなケースであれば変更は可能です。
(2)消滅時効
改正前の民法では、債権の消滅時効の年数というものは債権の種類ごとに細かく決められていました。しかし、それでは区分が複雑になっており、分かりにくいとの批判が絶えず寄せられていました。
そこで改正民法では、債権の種類別に定められていた消滅時効年数を、「債権者が消滅時効の権利を行使可能な時点(客観的な起算時点)から10年」、「債権者が消滅時効を行使可能であることを知った時点(主観的な起算時点)から5年」、が経過した場合には消滅時効により債権が時効によって消滅する、という形に統一されることになりました。
| 改正前 | 改正後 | |
| 消滅時効年数 | 具体例 | |
| 1年 | 宿泊料金、レンタカー料金、など |
|
| 2年 | 学校や塾の授業料・月謝、など | |
| 3年 | 病院やクリニックの診察費用、建設工事代金、など | |
| 5年 | 公共放送(NHK)の受信料、家賃、など | |
| 10年 | 友人から借りたお金(借金)、など | |
①改正による影響
改正民法では、客観的な起算点と主観的な起算点という2種類の起算点を定義していることから、時効における時間(期間)のマネジメントが大変になる、と考えるかもしれませんが、契約に則った履行請求権に関して言及すれば、一般的には客観的な起算点と主観的な起算点は一致することになりますので、原則としては、消滅時効の期間は債務を履行する時期から5年となります。
一方では、販売した商品の売掛金債権や工事の請負代金債権などのような、改正前の民法で短期間での消滅時効の対象となっている債権に関しては、消滅時効の期間が今までよりも長期化することになります。
②「時効の中断」および「時効の停止」の変更点
消滅時効とは、債権者としての権利を長い間行使していないのだからもう法律で保護する必要はありませんね、という趣旨の制度です。しかし、改正前民法においても、債務者に支払の請求や支払を求める裁判などを行った際には、消滅時効の時間の進み具合をゼロにする、というルールがあります。これは「時効の中断」と呼ばれています。
一方で、時効の進行がゼロにはならないものの、一時的に停止される場合もあります。これを「時効の停止」と言います。こういった専門的な法律用語はわかりにくいので、改正民法においては、「時効の中断」を「時効の更新」に、「時効の停止」を「時効の完成猶予」に、とそれぞれ改められることになりました。また、時効の完成猶予に関しては、自然災害などの問題が生じた場合には、改正前民法では 2 週間とされていたものが、3ヶ月に延長されました。
<改正民法における時効の更新および完成猶予>
| 時効の更新 | 時効の完成猶予 |
、等 |
|
改正民法では、協議によって時効の完成を猶予する、という制度が初めて設けられました。権利に関しての協議を実施する、という内容を書面で相互に合意した場合に、合意時点から1年間(これよりも短期間の協議期間を決めた場合は、その期間)、時効の完成が猶予されることになります。
この改正により、債務者が債務の存在を認めているというわけではないものの、債権者との間で協議することは可能、という意思表示をしているようなケースにおいて、提訴する(訴訟する)という選択肢の他に、書面で協議を実施する旨の合意を取り交わすというチョイスをすることで、最長で1年間までは時効の完成が猶予されることになります。この方法により、訴訟費用を減額することが可能になるでしょう。
(3)法定利率
改正前の民法第404条においては、「利息を生ずべき債権については別段の意思表示がないときは、その利率は年5分(=年率5%)とする」と定められていました。しかし、日本の銀行の貸出約定平均金利が年率1%程度、住宅ローンでも年率2%くらい、無担保融資(マイカーローン、教育ローン、などの消費性ローン)の場合であっても年率3~5%程まで金利が低下しており、(改正前民法上の)法定レートと実勢レートの乖離が問題になっていました。
その昔に銀行の預金金利が5%くらいの時代であれば、改正前民法上の法定レートの水準も実情を反映していた利率だったのですが、既に実態を反映しているとは言い難い水準となっていることから見直しの対象になりました。改正民法では、これまでの法定利率である年5%の固定利率を変更して、短期(貸付期間が1年未満のものを言います)の市場金利に連動する変動性となりました。
変動性とは言っても当初は年3%に固定して、その後3年ごとに利率を見直すこととしています。今回の法改正により、実勢レートとの乖離を防止することが可能になりますが、一度利息が発生した最初の時点での法定利率が、それ以後は適用されることになりますので、もし途中で法定レートの見直しが生じたとしても、途中で適用レートが変わることがない点には留意する必要があります。
<法定利率の見直し概要>
| 改正前民法 | 改正後民法 |
| 年5%
(ただし、商取引の際の商事法定利率は年6%) |
当初は年3% 以後3年毎に利率を見直し(ただし、利息が生じた最初の時点の法定利率がそれ以後は適用されることになる) |
①法定利率が適用される場面
この法定利率の規定は任意規定なので、実務においては契約の場面で、それぞれが定めた利率で約定されることになり、法定利率が適用される、という状況はあまり考えることはないかもしれません。法定利率が登場するシーンとしては、あまり利率について検討することがないことが多い、関連当事者の間における取引、遅延損害金を請求場合、人身を損害させてしまった賠償に関する逸失利益の計算の際の中間利息控除のための利率、などが挙げられます。
特に損害賠償に関しては、法定利率が大きく関わってくる可能性があります。なお、利息制限法においては、金銭消費貸借契約の約定利息の制限利率を年率15~20%としています。今回の法定利率を年 3%の引き下げたことへの対応を考慮するならば、利息制限法の制限利率の引き下げに関しても議論・検討される余地は十分にあるものと考えられます。
②中間利息控除についての取扱い
中間利息控除とは、例えば、交通事故で後遺症が残るような障害を負ってしまったために、健康であれば得られたと考えられる逸失利益や、保険を解約する際に生じる一時金の算定、などの場合に、現時点における損害額や保険一時金を計算する必要が生じた場合に利用されている方法のことです。
具体的には、将来発生する逸失利益を現在価値に引き直す(換算)するために、損害賠償額の算定基準時点から実際に逸失利益を得ることができたであろう時点までの利息相当額(中間利息)を控除することになります。中間利息控除に関しては、具体的な請求権の発生時点の法定利率が用いられることになっており、法定利率の変更が生じれば現在価値の金額も変更されることになります。
<中間利息控除の具体的計算例(1 年後の保険一時金50万円を現在価額に換算)>
| <法定利率が年5%(改正前)の場合> | 計算式 | |
| 現在価額 476,190 円 |
1年後の価額 500,000 円 |
500,000 円÷1.05% |
| <法定利率が年3%(改正後)の場合> | 計算式 | |
| 現在価額 485,436 円 |
1年後の価額 500,000 円 |
500,000 円÷1.03% |
(4)保証債務
今回の民法改正の中でも、保証人保護を拡充することは、重要なポイントになっています。親類縁者や友人・知人から保証人になって欲しい、とお願いされた個人が、断ることができないまま、また保証のリスクを熟知しないままで保証契約を締結してしまい、後になって債務を負担せざるを得ないようなケースがこれまでにもたくさんありました。
このような場合に保証人を保護するために、個人保証が可能なケースを制限して、個人保証が可能であっても、保証契約の時点で、契約締結後の情報提供義務を課す、ということで制約を付加することになりました。
①根保証契約における保証人の保護
根保証契約では、保証人となった人に当初に保証した債務の範囲を大幅に超える金額の債務弁済を要求される可能性があります。そこで、このような事態を回避するために、2004年(平成 16 年)に民法の一部を改正し、根保証契約に関しては、1)保証人が負う債務の上限額(極度額)等を契約内容に明記していないような根保証契約は無効とする、としました。
さらに、2)元本の確定事由が生じたような場合には、強制的に保証人が弁済の義務を負うことになる債務金額をフィックス(元本確定)させるようににして、根保証契約における保証人の保護が図られるようになりました。今回の民法改正では、個人を対象とする全ての根保証契約は、1)の極度額について契約の内容としなければ無効である、とともに、2)の元本確定事由の発生による債務金額の確定、も取り込まれており根保証契約の保証人保護を図るようにしています。
したがって、上記のルールの対象となる新規の賃貸借契約や物品購入の買掛金に関する根保証契約については、1)の極度額の金額の設定、つまり、「いくらにするか」を検討する必要があります。極度額の設定に関しては、保証人が弁済可能な金額の範囲や、その取引に保証人を入れる必要が本当にあるのか、いった点についても検討する必要があるでしょう。
<根保証契約改正のポイント>
- 極度額について契約の内容として明確にしなければ無効
- 元本の確定事由が拡張した場合
- 強制執行
- 担保権の実行
- 破産手続開始
- 相続発生 など
②個人保証の制限
改正民法においては、事業資金の融資を受けるケースなどで、個人が保証人になる際には、書面で保証契約を締結でするだけでは十分ではなく、経営者自身による保証といった一部の例外を除いて、保証契約の締結日前 の1 ヶ月以内に公正証書を作成することが必要となりました。
その公正証書の中に、あらかじめ保証人が保証債務を履行する意思を表示していない場合には、保証契約の効力は生じないこととなります。
<公正証書の作成が不要となる例外事項>
- 主たる債務者が法人で、保証人がその役員(理事や取締役など)である
- 主たる債務者が法人で、保証人がその法人の議決権の過半数を保有している
- 主たる債務者が個人事業主で、保証人がその共同経営者、あるいは配偶者である
③公証人による確認時の留意点
公正証書を作成する必要があるケースでは、主たる債務の債権者・債務者、元本、元本確定期日の定めの有無・内容、利息、違約金及び根保証契約の場合には極度額、加えて主たる債務者が債務を履行しない場合には債務全般に関して履行する意思を有していること等を公証人に口頭で伝える必要があります。
公証人は、上記のような内容について記録して、保証人となる予定の人に対して読み上げるか、あるいは閲覧させて、内容を確認し、了承の上で、署名押印を受けることになります。
④義務づけられる契約締結時の情報提供
保証人を保護するためには、一定の情報を提供する義務を負わせることが必要になります。保証の情報提供義務を負うシーンは以下の通りです。
<保証人に情報提供するべき場面と内容>
| 保証契約締結時 | 保証契約後に保証人から 情報提供を求められた場合 |
期限の利益を喪失した場合 |
| 債務者の財産状況などの情報提供を行う | 迅速に、債務者の弁済状況などの実態の情報提供を行う | 期限の利益を喪失したことを知ったときから2ヶ月以内にその旨を通知する |
(5)債権譲渡
債権は自由に譲渡できることが原則になっていますが、改正前民法では債権者と債務者の間での譲渡を禁止するという契約(譲渡禁止特約、と言います)を結ぶことが可能でした。これは立場が弱い人に対して保有している債権を悪金融業者・暴力金融会社などに譲渡されないようにする、弱者保護の観点から設けられていたと考えられます。
その一方で、譲渡禁止特約があるために債権者は資金調達の手段が狭められており、多様な資金調達方法をする障害になっている、との指摘があったことも事実でした。そこで、改正民法においては、債権譲渡の条件を緩和することにして、「譲渡禁止特約」から「譲渡制限特約」へと変更されることになりました。
この改正により、債権譲渡を禁止・制限することは可能ではあるものの、その禁止・制限に反して債権譲渡を行ったとしても法的効果は有効になる、とされました。債権回収や債権の有効活用が可能になる法改正であると言えます。
ただし、債務者にとっては不都合・不利益が生じる可能性もあるため、譲渡制限特約が付された債権が譲渡されてしまった場合には、譲渡債権相当金額を債務者が供託することで債務を免除される、となっています。
<債権譲渡制度の改正のポイント>
| 改正前民法 | 改正後民法 | |
| 債権譲渡自由の原則 | 譲渡禁止特約で制限可能 | 譲渡制限特約で制限可能だが、譲渡も可能 |
| 将来の債権譲渡 | 明文の規定はない | 可能 |
| 第三者への対抗要件 | 通知・承諾および登記が必要 | 改正前と同様 |
3.民法改正に対して必要な中小企業経営者の対応とは
前述した民法改正の主な5つのポイントはどれも会社経営においては重要なものばかりです。例えば、消滅時効や債務保証など、実務的に大きな影響を与える法改正もなされていることから、法務面は顧問弁護士や法務部に任せてある、ということではなく、経営者自らも契約などに直結するような改正事項を把握・理解しておくことは極めて重要である、と言えます。
もちろん法律の詳しい内容・運用まで経営者が覚えておく必要はありませんが、例えば、顧問弁護士や契約している法律事務所などに改正民法の概要やポイントなどをレクチャーしてもらう勉強会を開催する、といった努力は必要ではないでしょうか。
また、営業部隊など契約実務を担っている従業員も含めて、上記のような勉強会を開催して出席してもらうことも必要かもしれません。法律知識に疎い従業員が契約書を作成しているような場合には、もし契約内容に法律的な不備があったとしても気付かないまま契約交渉を進めてしまい、最終的に自社にとって非常に不利益を生じさせる契約をせざるを得なくなってしまうリスクがあります。
したがって、経営者のみならず従業員も含めて、今回の民法改正のポイントを掴んでおくことは会社全体にとっての利益に繋がる、という意識を持つことが非常に大切だと考えられます。
また、これからの新規契約だけでなく、既存の契約に関しても前述した主な5つの法改正のポイントに関する契約条項を見直してみることも必要になります。原則としては、契約日が改正民法の施行日前であれば改正前の民法が適用されることになりますが、改正民法施行日前の契約が更新される場合の合意書が別途締結されていれば、改正後民法が適用される可能性が高いと考えられます。なお、契約書が自動更新の場合は改正前民法が適用さえるでしょう。
多くの中小企業においては、後継者不足や人材不足などを経営課題の最重要項目に挙げるケースが多いようですが、その一方で法務人材の不足、という課題を挙げる経営者も少なくありません。
自社の顧問として弁護士や司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士、などの外部人材を活用することが一般的になっていますが、その中でも弁護士に関しては敷居が高く費用も高い、と考えている経営者が多いことから、顧問弁護士との契約には二の足を踏んでいるケースも見受けられます。
しかし、専門家(プロフェッショナル)との顧問契約により、自社内の法務部門の従業員のレベルアップを図ることが可能になります。実際に東商の2019年のアンケート(「中小企業の法務対応に関するアンケート調査」)によると、法務担当者(含む兼任者)を設置している企業では、売上増加傾向の割合が大きくなる、とされています。
つまり、例えば今回の民法改正のようなケースにおいて、改正内容を理解して契約実務に活用している企業は、売上の増加に寄与するような、社内における法務サービスを提供することができている、と言うことが言えるのではないでしょうか。
今回の民法改正のみならず、労働問題、事業承継、など、中小企業を取り巻く法務問題には様々なものが存在しています。したがって、それらの法務問題に対応するためにも、専門家のサポートを受けつつ、経営者と従業員(特に法務部門)が一体となって対応策を検討することが必要だと考えられます。
<まとめ>
 2020年4月に施行された改正民法は、「平成の大改正」(施行は令和2年ですが、法改正の審議や成立が平成だったため)と呼ばれており、120年以上もの長きに渡って、基本的には、手が付けられることのなかった民法を「今」の日本の実情に合わせて大きく改めることになったものです。
2020年4月に施行された改正民法は、「平成の大改正」(施行は令和2年ですが、法改正の審議や成立が平成だったため)と呼ばれており、120年以上もの長きに渡って、基本的には、手が付けられることのなかった民法を「今」の日本の実情に合わせて大きく改めることになったものです。
法律を守ることはとても大切ですが、実際の社会生活と乖離してしまった法律については、解釈を変更する、といった方法での対応も可能ではあるものの、必要に応じて改正しなければならないと考えます。
それと同時に、改正された背景や理由を理解したうえで、実務において正しく活用することも法律の使い方としては重要である、と考えます。日本は法治国家であり、経済面においても民法や商法、会社法などの多くの法律が存在します。このような法律を十分に踏まえたうえで、わが国は経済面でこれまで飛躍的な進化を遂げてきました。
そのような環境下において、法律を遵守するとともに自由な経済活動を進めてこれたからこそ、今の日本の姿があるのだと思われます。もちろん行き過ぎた経済活動に対しては法的な規制がかかる可能性もありますし、社会的な批判が浴びせられることもあるでしょう。
つまり、必要な法的規制と自由な経済活動のバランスを十分に考えながら、社会生活の発展を考える必要があるのです。今回改正された民法も長い期間を経ていく中で、徐々に実情にそぐわなくなってくる可能性がありますが、その際にも、今回のように、十分な議論を踏まえたうえで、経済活動に資するような改正が行われることを期待します。
関連記事:債権者の権利とは?取引の際に気を付けておくポイントを詳細解説