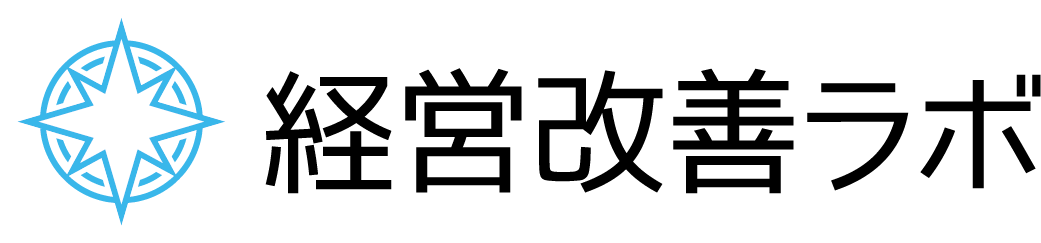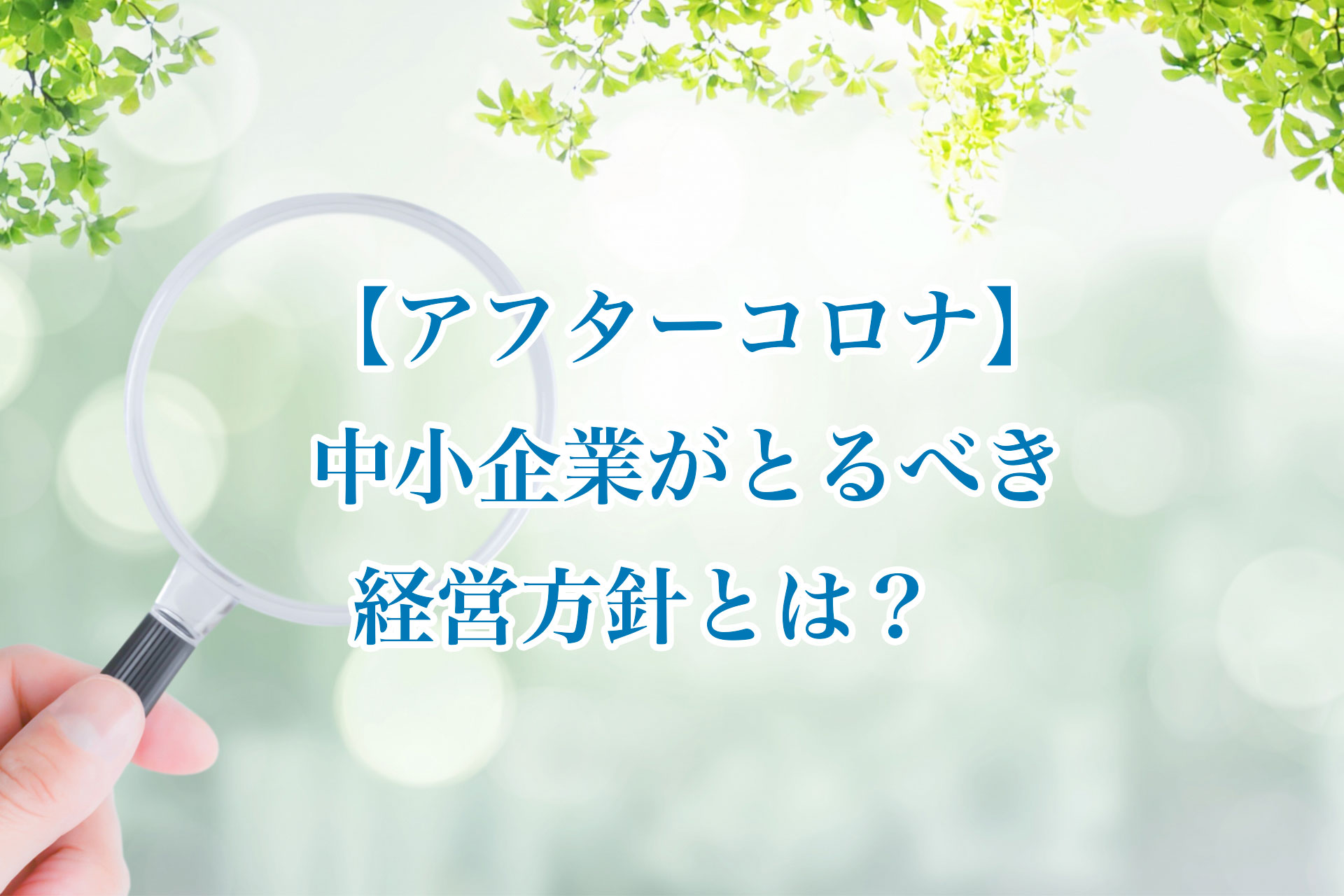我が国の農業は、少子高齢化や後継者不足などの理由から効率化や生産性向上には簡単には取り組めないという課題に直面しています。そこでスマート農業と言われる解決策に大きな注目が集まっています。スマート農業とはどのような農業のことを言うのでしょうか。スマート農業の概要について解説します。
次いで、具体的なスマート農業の導入事例について紹介したうえで、実際にスマート農業に取り組む場合の課題とその対策についても説明します。
1.スマート農業とは

日本の農業に対しては、今後の国土利用の効率性や食料自給率の重要性などの観点から、大きな注目が集まってはいるものの、実際には多くの農家が後継者不在や働き手の高齢化などの問題から農業という事業の継続に悩んでいます。そこで、「スマート農業」と呼ばれる新たな農業への取り組み方に対して大きな期待が寄せられています。
「スマート農業」とは、どのような農業のことを指しているのでしょうか。従来の農業には「キツイ、汚い、危険」といういわゆる3Kのイメージがあり、実際に主に高齢者が中心となり人の手で重労働を強いられる、といったものでしたが、機械化のみならずデジタル技術を活用して省力化・高付加価値を目指す農業のことをスマート農業と呼んでいます。スマート農業には以下のような手法を挙げることができます。
(1)ロボット技術の活用
農業においては長年農業に従事してきた熟練した労働者の存在が不可欠でした。長年の経験から導き出される最適解を農産物の生産に反映させることが重要だったと考えられます。しかし、相手は自然であるため、どのような自然環境下であっても常に正しい解答=対応策を選択できるというものでもありません。
また、人間の手による農作業には疲れてしまうという問題が必ず生じますが、機械であれば基本的には動力さえあれば基本的には動き続けることは可能です。そこでロボット技術を農業分野にも応用して農作業の自動化や省力化を図ることが可能になっています。
また、例えばまっすぐに苗を植えることは簡単そうに見えて熟練の技が必要な作業ですが、これをロボットに記憶させて作業させれば再現性の高い同様の作業が何回でも繰り返すことが可能です。さらに危険な傾斜した田畑での農作業であってもロボットを利用すれば、人間がケガをするリスクを大きく減らすこともできます。このように今後の農作業においてはロボット技術の活用は欠かせないと言えるのです。具体的なロボット技術の活用方法を紹介します。
①自走トラクター
農業用のトラクターとは、荷物を牽引する車両のことです。トラクターが登場する前までは主に牛馬に荷物を引かせていましたが、現在ではトラクターに収穫した農作物を運搬させたり、田畑を耕す鋤のような器具をトラクターに装着して耕運機のような作業をさせたり、とトラクターは万能的な働き方をする農業機械です。
これまではトラクターの運転は人間が運転席に座って速度や移動方向などを指示(運転)する必要がありました。実際には平坦ではない田畑での作業などでは横転事故などが発生することもあり必ずしも安全な作業とは言えない部分もありました。また、単調で同じ作業を何回も繰り返す必要があることから、農作業従事者の肉体的・精神的疲労はけして軽いものではありませんでした。
そこで、例えば耕す田んぼの地形をあらかじめトラクターにインプットしておいて、無線技術(ラジコン)などを利用して、人間が運転席にいなくても自動でトラクターを走らせることが可能になっています。この技術を利用すれば、必ずしも人間が田畑にいる必要はなく、遠隔地からトラクターを運転することも可能になります。
悪天候で外での作業が困難な場合や、農作業従事者の誰かが病気になって人手が足りないような場合でも、ロボット技術を活用した自走トラクターがあれば、田植えや収穫のタイミングを逃すことなく農作業をすることが可能になるのです。
現在では大学などの研究機関と農家との提携(コラボレーション)も進んでおり、例えばGPSシステムを用いたオートマチックで走行可能なトラクターの開発なども進んでいます。ロボット技術利用による自走トラクターの開発は、農業従事者の後継者不足に対して大きなサポートになるものと期待されています。
②収穫ロボット
農作業で大変な作業はたくさんありますが、その中でも農作物の収穫作業はとても気を使う作業のひとつでしょう。米や麦などの収穫に比べると、ブドウや桃などの果物の収穫は、農作物を傷付けてしまえば売り物にならなくなってしまうので、これまでは基本的には人の手で丁寧に収穫してきました。
ところがロボット技術の進化により、まるで人間の手で収穫したように丁寧に果物を傷付けずに収穫することが可能になっています。前述したトラクターの場合と同様に果樹園の地形を記憶させて自走可能になるのみならず、果物の完熟度合いなどをセンサーで確認して最適な収穫時期を判別することもできるのです。
収穫の際には果実を傷付けないように、果物の種類に応じた収穫用のアームをロボットに取り付けて丁寧に作業ができるようにしている収穫ロボットが一般的です。
③ドローンの農業への利用
ドローンの特性である、高低差のある移動や素早い空間移動などを利用してドローンは農業にも大いに活躍しています。これまでは農薬散布作業に無人のドローンが利用されるケースは多かったのですが、現在では更に利用目的が広がり、ドローンで撮影した農場などの写真から農作物の生育状況を確認して肥料が必要かどうかのばらつき状況を判別する元データとして利用する、などとして活用されています。
農薬散布については、米国の大農場などでは航空機を利用した大規模な散布が行われていたりしますが、コストが高く、また日本のように狭い農場ながら高低差が大きな農場での利用は困難だったものが、ドローンの登場により、安いコストで安全に農薬散布が可能になったと言えます。
(2)ICTの活用
ICTとはInternet Communication and Technologyのことで、通信技術を活用して人間と人間、あるいは人間とインターネットが繋がる技術(テクノロジー)を言います。これまでの農業は長年の実際の農作業経験に基づく、農業従事者に蓄積された知見とカンに基づいて仕事が行われてきましたが、ICTを活用することにより、様々なデータを分析して農作業に活用することができるようになります。
また、それらのデータをベースに今後の農作物の発育状況や農作物に害をなす害虫や病気などの発生をAI技術を活用して予測することが可能になっています。つまり、科学的なデータを踏まえた予測に基づいて、適切な対策を早期に実施することが可能になっている、とも言えるのです。
これまでは自然の脅威に対しては、基本的に何か事が起こってから対症療法的に対応することしかできなかったことが、能動的に防衛策を打ち出せることにより、収穫量や生産金額を安定的に予想することが可能になってきている、ともいえるのです。
①農業データの連携インフラ
従来の農業はそれぞれ独立した農家が各自主体となって農業を営んでいたこともあり、農協などを通じた情報の共有などは多少はあったものの、地域で農家が情報を共有できるような仕組みには乏しかったものと考えられます。
例えば、地域における今後の天気や気温、降水量などの情報が一斉に共有できるようインフラが整備されている、と言えるようなケースは少なかったのではないでしょうか。しかし、デジタル技術の進展に伴い、天候のみならず、外注発生リスクの予想、台風被害の予測、自然災害による農産物被害額の推計、などを行うことが可能になってきています。
具体的には、2019年4月から農業に関するデータを連携・共有する基盤として「WAGRI(ワグリ)」というプラットフォームが稼働しています。これは、今まで偏在していた大学などの研究機関や民間施設のデータについて、ICTを活用して相互連携させることができる仕組みなのです。WAGERIは生産段階での利用にとどまらず、その先の販売や消費といった段階においてもデータ連携をすることが検討されており、2022年には新たなスマート・フード・チェーン・システムが構築される予定となっています。
②ビッグデータの収集と活用
従来の農業にはICTなどの新たなデジタル技術の利用という発想がなかったことから、せっかくの貴重な情報が役に立たないで死蔵されてしまったようなケースは多かったのではないでしょうか。しかし、今日においては*ビッグデータを収集・活用することが可能なインフラが整いつつあります。
農業に関するデータにも様々なものがありますが、それらのデータを収集したうえでICTを活用して、生産農家に役立つような形に加工して提供する、ということはこれからのスマート農業にとっては極めて重要なポイントになるでしょう。
2.ベンチャー企業によるスマート農業への取組事例

スマート農業の分野においては世界中でスタートアップを含む多くのベンチャー企業が参入を図っています。大きく進化したロボットやIOTに関する技術を活用することで、他社とは差別化したサービスの提供が可能になっていることがその理由です。本稿では具体的な取組事例を紹介します。
(1)ロボット技術を活用したスマート農業の取組事例
①inaho
イナホ株式会社が提供しているRaaS(Robot as a Service)というサービスモデルを利用した自動野菜収穫ロボットの活用により、高額な設備投資を抑制することが可能になり、人材不足にも対応することができるようになります。このサービスをinahoと呼んでいます。
(参考URL: https://inaho.co/)
RaaSとは、ロボットそのものを販売することなく、サービスとして利用者に提供する仕組みのことを言います。具体的には、収穫ロボットを農家などに無料でレンタルをします。そして、ロボットが収穫した農産物の収穫量に応じてロボット使用料を支払う、ということになります。
したがって、これまでの農業機械と比較すると、最初の導入費用(イニシャル・コスト)がほぼ不要であること、維持管理費用(メンテナンス・コスト)も不要であること、そして収穫ロボットの利用期間を選択可能であること、などがメリットとなっています。
inahoのRaaSモデルを利用した場合と収穫ロボットを購入した場合との比較表は以下の通りです。
現在inahoで対応可能な作物はアスパラガスのみですが、今後は、キュウリ、トマト、ナス、ピーマン、いちご、等への種類を拡大していく予定です。これまでは、これらの野菜は個体によって成長速度にバラツキがあるので、どうしても完熟の判断をするためにも人間の手による収穫が必要でした。
しかしinahoでは収穫してよいかどうかをAIが判断してロボットが収穫するので、最適な収穫時期を選択することが可能になっています。
②Legmin
Legminは株式会社レグミンが提供している種蒔きから収穫までをロボット技術を活用して自動化するサービスのことです。例えば、自律走行するロボットを用いて種蒔き、栽培、収穫を効率化して余計な手間やコストを極力抑制したり、画像解析による病気や害虫を早期に発見したり、と生産性の向上に大きく役立つサービスを展開しています。
(参考URL:https://legmin.co.jp/)
当社は実際に自社農場を保有して農作物の生産を行っています。そこで実際に得た経験や課題に基づいて、自社サービスの開発や改善に役立てています。
③オプティム
株式会社オプティムは、世界で初となるピンポイントでの農薬散布技術をはじめ、ロボティックスなどの活用で、農業の高収益化・省力化の実現を目標としています。特にドローン技術を活用したスマート農業へのアプローチには定評があります。
例えば、広範囲な田畑などへの監視・巡回作業(田畑に対するスキャンの実施)、分析するための画像収集(農産物生育状況モニタリング)、前述したピンポイントでの農薬散布、などをドローン技術を用いたサービスとして挙げることが可能です。
(2)ICTを活用したスマート農業の取組事例
①Plantect
自動車の部品製造で世界的に有名なボッシュがスマート農業の分野にも進出しています。このプランテクトというサービスは、データ活用を基本的な思想としており、センサー技術によるビニール・ハウス内の環境を監視(モニタリング)して、AIを利用した農産物に対する病気や被害を予測します。
(参考URL:http://www.bosch-plantect.jp/)
自動車部本の開発で培った独自の技術を用いて、様々なセンサー(温度・湿度、二酸化炭素、日当たり、など)を開発し、ビニール・ハウス内で生産される全て農産物を対象に、ビニール・ハウス内の状況の可視化(見える化)が可能になっています。
各種のセンサーから収集されたデータは手元にあるタブレッやスマホなどでどこにいても、そしていつでも確認することができるようになっています。さらに、トマトの葉かび病やうどんこ病、きゅうりといちごのうどんこ病、などの農業生産者が日常的に困っている病気による被害のリスクデータを予測して提供することが可能となっています。
プランテクトには以下の2つのプランがあります。
②ZeRo.agri
ZeRo.agriとは株式会社ルートレック・ネットワークスが提供しているサービスで、AIを活用して土壌の環境をコントロールするものです。
(参考URL:https://www.routrek.co.jp/)
農地というものは、生産者が長い年月をかけて肥沃な土壌や農産物に適した栄養状態のバランスが良い土地などを育成してきた、という歴史があります。したがって土壌作りには経験と時間が必要である、という考え方がこれまでは一般的でした。
そこでZeRo.agriでは、過去の天候、土壌の水分量、といった様々な環境に関するデータや潅水量、施肥量などといった様々な栽培に関するデータを保有して、その膨大なデータを分析することで適切な土壌へと育成させることが可能になっているのです。土壌に関するサービス提供者はまだ数が少ないので貴重なスマート農業への参加者であると言えます。
また、ZeRo.agriは「養液土耕向け AI潅水施肥ロボット」というサービスも提供しています。養液土耕とは、いかに少ない水量で効率良く生育させることができるか、という考え方に基づいて、点滴潅水(チューブの穴から少しずつ土壌に浸透する速さで水滴をポタポタと垂らすこと)で、水量の節約のみならず農作物の生育を改善することも可能になります。
ZeRo.agriのAI潅水施肥ロボットは、利用者が設定した土壌の水分量や養液内の肥料濃度などに沿って、自動的に潅水や施肥をさせることが可能になっています。また、土壌の水分量や土壌のEC値(土壌中の塩類濃度)、そして天候や日射量などの環境に関するデータや、潅水量や施肥量などの栽培に関するデータを、パソコンやスマホを利用することで農場の外から監視(モニタリング)することもできます。
3.スマート農業における問題点

これまで説明してきたようにスマート農業は様々な切り口から徐々に普及してきているものと考えられますが、今後さらにスマート農業を拡大させるためにはどのような課題があるのでしょうか。スマート農業拡大における課題とその対策について解説します。
(1)コストが高い
最新のデジタル技術を搭載した農業機械などは、これまでの汎用タイプの農機具に比べると値段も高く導入に二の足を踏みがちになってしまうことが十分に考えられます。零細農家であれば尚更で、高価な機械を揃える余裕はないでしょう。
また、費用対効果を見積もることが難しい点も挙げられます。高い費用をかけてロボット技術やIOT技術を活用した高価な農業機械を購入したとしても、どのくらいの作業効率化が可能なのか、どのくらい生産性が向上するのか、シミュレーションは可能であっても、例えば、突発的な自然災害による損失が発生した場合にはどうすればよいのか、などの心配もしなければなりません。
まず高コストの問題ですが、この点に関しては、前述したinahoのRaaSでも触れましたが、農業機械の販売・購入ではなくリースを活用する方法が考えられます。時代の流れにおいても「所有から利用へ」という消費者側の心理的変化が起こっているため、リース活用の拡大は重要なポイントになるでしょう。
また、利用者が少ないためどうしても高額になりがちな農業機械ですが、今後市場や利用者の拡大と同時に、農機具メーカーによる不断の努力による製造コスト及び販売価格(若しくはリース費用)の低減が図られることも大いに期待できるので、多くの農業従事者の手に届きやすい価格へと移行していくことが期待されています。
コストを抑える方法を考える工程管理とは?無駄を省いて効率化するための全手法を大公開の記事もご覧ください。
(2)農業従事者のITリテラシーが低い
2つめの課題として、農業に従事している人々の*ITリテラシーが低い、というものが挙げられます。その原因としては、就農者には高齢者が多いので、そもそも新しいデジタル技術に触れる機会が少なく、また高齢者以外の人々も含めて、スマート農業で活用されているロボット技術やIOT儀重などを勉強する機会も恵まれていなかったことがあります。
この課題への対応策としては、JAや農機具メーカーなどが農業従事者向けにスマート農業用の機械の使い方の勉強会を開催することが必要不可欠だと思われます。利用者は、デジタル技術の細かい内容までは必要ではありません。具体的に、どういったシーンでどのようにその機械を動かせばよいのか、不具合が生じた時にはどう対処すればよいのか、など実務的な講習を複数回実施することが有用です。
また、農業従事者の後継者不足の問題とも重複するのですが、ITリテラシーの向上には人材の育成も非常に重要です。大切なことは、農機具メーカーと農業従事者を繋ぐことができる「中間的な(ミドル層の)人材」を育成することです。もちろん農家の人でそのような人材がいれば全く問題はありませんが、例えば、地方自治体やJAの職員、地域金融機関に勤務している人、地元に根差している農機具メーカー代理店の人、など、農機具メーカーの使用している言語を農業従事者に対して翻訳(理解できるように丁寧に説明)可能な人材を育成することが対策になります。
全国の*農業大学校では、農業従事者自身がスマート農業の技術を理解して、農業経営に役立てることができるようなサポートを行っています。例として、全国の農業大学校においてはスマート農業を取り入れた講義・実習を行っています。2019年からは農業大学校のみならず、農業高校においても同様の取組を実施しています。
「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく」考え方に関するDXとは? 概要と推進するための手順を解説しますの記事もご覧ください。
(3)農業市場の縮小
農業を巡る極めて重要かつ難しい課題として、我が国の農業市場そのものが縮小しているという点が挙げられます。農産物の国内生産額は米を中心に減少が続いており、農業所得はピークの1978年の5.4兆円から2009年には2.6兆円とほぼ半減しています(なお、最近(2012年)では3.0兆円とやや持ち直している傾向が見受けられます。
(参考資料:農林水産省「生産農業所得統計」https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h26/h26_h/trend/part1/chap2/c2_1_01.html)
これは少子高齢化の急激な進展により、農業従事人口そのものが減少しており、農業を継ぐ人が少なくなっていることが理由として挙げられます。絶対的な人口数の減少が止まらない中で、農業人口を増やすことは非常に難しいと言わざるを得ません。
製造業やサービス業などの他の業種においても人材不足は経営を揺るがしかねない最重要の課題となっており、他の業種から農業への大量の労働力流入ということも考えにくい状態です。スマート農業の普及拡大により、農業への働き手が増加することも考えられますが、これはスマート農業の普及スピードが早いか、就農人口の減少が早いか、という話になってしまいます。
したがって、農機具メーカーの中にはこのように困難な状況にある日本の農業マーケットに固執することなく、海外の農業マーケットに向けてスマート農業の拡大を狙っている企業も増えているようです。農業市場が拡大していると言われている中国、ベトナム、タイ、といった海外市場に進出している農機具メーカーは増えています。
日本の農業市場においては大規模な実証実験(フィージビリティ・スタディ)の機会を得ることはなかなか難しいと思われますが、前述した海外各国の農業市場においては、様々な実証実験を実行することができます。
そして、重要なことは海外で培ったスマート農業の技術を日本国内の農業市場にマッチするように改善して逆輸入することで、新規開発費用などの軽減が図れるという点です。つまり、国内農市場への導入が円滑に進められる可能性が高くなるのです。
また、国内の就農者には海外の人材をもっと活用する必要がある、という意見も根強く、外国人労働者を増やすためには、母国語による相談窓口の整備、実習先変更・調整に対するサポート、実習生の一時的なステイ先の提供、などの様々な支援策がまだまだ必要な状況ではあるものの、今後ますます不足するであろう国内農業従事者の対策としては、喫緊の対応が求められる論点です。
スマート農業の普及拡大と同時にスマート農業の担い手となる就農者の確保も極めて重要です。これまでは日本国内を中心に農業のことを考えていたかもしれませんが、海外農業市場への進出・活用と外国人労働者の農業への就労推進、は今後のスマート農業の展開にとっては大切なポイントになるものと考えられます。
<まとめ>

スマート農業は、往々にして、新しい農業、あるいは、AI(人工知能などを駆使した農業、といった先進的なイメージばかりが先行しがちな傾向にあります。しかしながら、日本の農業市場がマクロ環境として、構造的に縮小している状況を考えると、実際のところは、簡単にスマート農業の市場が拡大できる、と考えるのは非常に難しいとと言わざるを得ません。
このポイントに関しては、2000年代以降に話題となった植物工場(工場内で農産物を栽培・育成する方法)における、これまでの道のりを振り返ってみるとわかりやすいかもしれません。日本の農業市場の拡大に対しては、従来から地方自治体やJAなどが主体となりつつ、取り組む企業などの担い手確保を推進することはもちろん、企業側の積極的な活動にも大きな期待が寄せられています。
換言すると、スマート農業の普及やマーケットの拡大を待つのではなく、能動的に自分たちの商品・製品を販売・提供することが可能なマーケット環境の整備に自ら関与していくことが期待されているのです。例えば、企業(メーカー)が仲介をしつつ、耕作が放棄されている農地や離農が予定されている農地など、規模の拡大を目指している大規模な農業事業者や新たに農業参入を計画している民間企業などに斡旋したり、企業自身が関係者を増やしながらスマート農業のモデルとなる農地を立ち上げたり、することなどを考えることが可能です。
どのケースであっても、企業(メーカー)自身がマーケットそのものを作り上げる環境を整えることに能動的に関与・参加することがポイントです。その際には、前述したような企業側と農業従事者側の双方の事情に詳しい人材との連携重要な鍵となります。企業側の積極的な取り組みによる本格的なスマート農業の普及拡大に期待します。