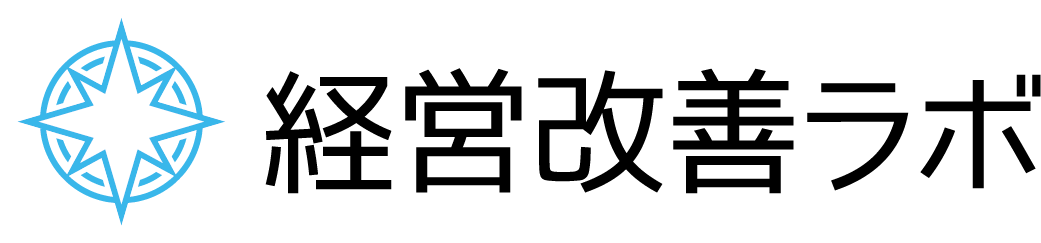「原価差異ってなんですか?」と質問されてすぐに答えられる経営者は多くはないかもしれません。
原価差異とは、原材料の消費価格の差異、労務費の賃率の差異、製造間接費の配賦費用の差異、などを全て含めたものをいいます。
原価差異とは原価の予定価額と実際差額との差額のことを指している(原価差異=標準原価-実際原価)とよくいわれていますが、原価差異は標準原価計算を前提としているので、「原価差異=実際原価-標準原価」、つまり原価差異は標準原価と実際原価の差異とする考え方が正しいといえます。
この原価差異には有利差異と不利差異というものがあります。
本稿においては、有利差異と不利差異の概要、有利差異と不利差異の求め方、原価差異分析の活用、(まとめ)原価差異分析を上手く活用するためには、などについて詳しく解説します。
1.有利差異と不利差異の概要
 有利差異(Favorable Variance)とは、実際原価が標準原価よりも少なかった状態のこと(実際原価 < 標準原価)を言います。また、「原価差異= 実際原価-標準原価」なので、「原価差異 < 0」となります。
有利差異(Favorable Variance)とは、実際原価が標準原価よりも少なかった状態のこと(実際原価 < 標準原価)を言います。また、「原価差異= 実際原価-標準原価」なので、「原価差異 < 0」となります。
一方、不利差異(Unfavorable Variance)とは、実際原価が標準原価よりも多かった状態のこと(実際原価 > 標準原価)を言います。また、有利差異と同様に「原価差異= 実際原価-標準原価」なので、「原価差異 > 0」 となります。
標準原価をベースとして、実際原価がこれよりも少ない場合には「有利」、あるいは多い場合に「不利」と呼んでいるだけのことではあります。「原価差異 < 0」の場合を「有利差異」、「原価差異 > 0」 の場合を「不利差異」と呼称しているというわけです。
実際原価を真実の原価と捉えている立場からすれば、標準原価に基づいて実際原価に引き直した時に、有利差異の場合であれば、標準原価に比べて実際原価が減少することになり、不利差異の場合であれば、標準原価に比べて実際原価が増加する、ということになります。
実際原価を200、標準原価を180とすると、原価差異は 200 - 180 = 20、と実際原価が標準原価より多いので不利差異となります。また、この原価差異の残高が借方に現れることから「借方差異」とも呼ばれています。
また、実際原価が190、標準原価が240とすると
原価差異は 190 - 240 = ▲50と実際原価が標準原価より少なくなるので有利差異となります。この場合は、貸方差異(原価差異の残高が貸方に現れるから)で有利差異となります。数字マイナスになるから不利差異だろう、と考えてしまうのは言葉の印象に引っ張られているだけでしょう。
原価差異の考え方はあくまで標準原価が基準となっているので、有利差異、不利差異、と言う言葉は以下のように置換するとわかりやすくなるのではないでしょうか。「Favorable Variance」はプラス差異(標準原価に比べて原価が減少して企業にとってプラス(有利)に働く)、一方で「Unfavorable Variance」はマイナス差異(標準原価に比べて原価が増加して企業に-(不利)に働く)と考えるのです。
一義的には、原価差異は仕掛品や製品と同様に貸借対照表(B/S)の借方勘定に集約されて(損益計算書(P/Lの場合もあります)、最終的には売上原価に配賦されることになるので損益計算書(P/L)の借方勘定となる、ということが言えます。つまり、原価差異は借方勘定なのです。
つまり、実際原価が標準原価に比べて増加する場合であれば借方差異となり、逆に減少する場合であれば貸方差異になる、ということになります。したがって、原価差異勘定の借方に残高がある場合には、原価差異 > 0 となるので不利差異(借方差異)と呼称し、原価差異勘定の貸方に残高がある場合には、原価差異 < 0 となるので有利差異(貸方差異)と呼称しているだけの話なのです。
2.有利差異と不利差異の求め方
原価差異の処理に関しては実際に発生した費用の残りというイメージに近いものがあります。原価差異が生じた場合には、会計年度の年度末に売上原価から加減することになります。具体的には、不利差異であれば売上原価に加算し、有利差異であれば売上原価から減算するのです。不利差異の場合においては発生した費用が売上原価にはなっていないので加算することになります。
反対に、有利差異の場合であれば費用のマイナスというイメージになります。節約ができたということなので、売上原価から減算するという処理を実施します。どういうケースであれば不利差異となり、どういうケースであれば有利差異になるのか、という事に関しては、材料消費価格差異、賃率差異、製造間接費配賦差異、のそれぞれついて理由があります。
(1)材料消費価格差異について
具体例として、自動車の製造企業において材料の標準価格が500円だったとして、実際の材料費が600円だったとすると、600円 - 500円 = 100円となり、この100円が「材料費価格差異」となります。より深く理解するために、さらに事例を挙げて考えてみましょう。
<事例①>
原材料の実際単価 :@20円
原材料の標準単価 :@15円
当月の材料消費量 :50㎏(ただし、全て直接材料として消費)
上記の事例において原材料を消費した場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 750 | 材料 | 750 |
単純に標準単価(@15円)×材料消費量(50㎏)=750円、と計算しただけで、全部直接材料なので仕掛品として計上します。そして、実際材料費は@20円×50㎏=1,000円となります。当初は750円として製品の原価を考えて計算していたのに実際には1,000円もかかってしまったので、250円は余分に製造原価がかかってしまっていた、ということになります。
そこで、考え方としては、材料750円を消費したとして材料(資産)を750円分だけ減少させます。資産である材料が貸方にあることから材料が750円分減少します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 750 | 材料 | 750 |
しかし、実際の消費額は1,000円になったわけなので、材料の減少分が実際消費額の1,000円になるように1,000円 ― 750円 = 250円分だけ、さらに材料を減少させる必要があります。つまり、実際の消費額に寄せていくという仕訳をしなければなりません。
先ほどの仕訳では、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 750 | 材料 | 750 |
だったので、貸方の材料を1,000円にするために、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| – | – | 材料 | 250 |
と、合計したら貸方の材料が1,000円になるようにすればよいのです。こうして辻褄を合わせるようにします。これで貸方の処理はできましたが、借方はどのようにすればよいのでしょうか。貸方だけ材料に250円を加えても借方が250円抜けていた場合にはバランスを取ることができません。そこでバランスをとるために「材料消費価格差異」という勘定科目を使います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 材料費価格差異 | 250 | 材料 | 250 |
つまり、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 750 | 材料 | 1000 |
| 材料費価格差異 | 250 | ||
となるのです。
この差異は、実際に発生した製造費用の一部である、と考えられます。実際に生じた製造原価で製品の原価となっているのは750円だけでしたので、上記の例においては借方に「材料消費価格差異」を記載してバランスを取りました。このように借方に登場する材料消費価格差異のことを不利差異(借方差異)と呼んでいることについては既に説明しました。
不利差異がある、ということは原価に無駄があったという意味になります。なぜかというと、標準消費額750円というのはある意味では標準的な価額なわけで、750円の材料費で製造できる思っていたら実際には消費額が1,000円もかかってしまった、というわけになります。
と言うことで、不利差異(借方差異)というのは無駄な差異、原価の無駄遣い、ということを意味しています。そしてこのような場合を、「材料消費価格差異が不利差異(借方差異)のケース」ということになります。
<事例②>
原材料の実際単価 :@30円
原材料の標準単価 :@40円
当月の材料消費量 :100㎏(ただし、全て直接材料として消費)
上記の事例②の場合では、実際単価は@30円、そして標準単価は@40円であり、材料消費価格差異が有利差異になるのは、標準単価>実際単価、の場合になります。事例②を最初に仕訳した場合には、標準単価を使うので
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 4000 | 材料 | 4000 |
となります。この仕訳の意味は、材料を消費した際に材料という資産4,000円分が減少した、ということになります。これに対して実際の消費額は実際単価×数量なので、@30円×100㎏=3,000円です。つまり、4,000円-3,000円=1,000円分だけ材料の減少分を取り消すことが必要になります。
少しややこしいのですが、資産(材料)の減少は貸方に計上します。この減少分を取り消すと考えるのです。したがって、材料を借方に計上すればよいのです。
つまり、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 材料 | 1000 | 材料消費価格差異 | 1,000 |
という仕訳を合体させればよいのです。
そして最終的には、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 4,000 | 材料 | 4,000 |
| 材料 | 1,000 | 材料消費価格差異 | 1,000 |
という仕訳が生成されることになります。
上記の差異のことを、前述したように、有利差異(貸方差異)と呼んでいます。実際に、貸方の方に材料消費価格差異1,000円が計上されています。したがって、費用的には節約していることになるのです。4,000円かかるはずだったものが3,000円で済んでいるわけなので、ある意味では、材料費を節約できたというわけになります。
(2)賃率差異
材料費価格差異に続いては、労務費における重要な要素である賃率の差異に関して詳しく説明します。標準賃率を利用して労務費を計算することで標準消費額を算出することが可能になります。ただし、標準消費額はあくまで当初における仮定(予定)の話であって、実際の話とは異なります。
標準賃率とは、最初に設定しておく(理想とすべき)賃率のことを意味していますが、標準消費額は以下の算式で計算をします。
ここで事例を挙げて解説します。ある労働者(直接工)の直接作業時間は8時間でした。なお、この労働者(直接工)の賃金は標準賃率(@1,000円)を使用して計算をするものとしましょう。この事例の重要なポイントは、賃金を消費した場合には賃金・給料の勘定から仕掛品や製造間接費の勘定へと振り替えていく点になります。
この事例では労働者(直接工)の直接作業時間ということなので直接労務費となり、仕掛品へと振り替えていくことになるのです。実際の算出方法としては、@1,000円が標準賃率なので、でこの賃率に直接作業時間の8時間をかけた8,000円が仕掛品になります。
したがって、仕訳は
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 8,000 | 賃金・給料 | 8,000 |
となります。
企業としては、賃金・給料を支払う(消費する)立場になるので、賃金・給料は貸方(右側)に仕訳されます。
なお、標準賃率を利用して標準消費額を算出場合には実際の消費額と差異が発生します。なぜならば、標準賃率に実際の直接作業時間を乗じて計算することになるので、実際賃率と標準賃率の差異が実際消費額と標準消費額の差異になると言えるのです。前述したように、材料費の場合も不利差異や有利差異が生じていましたが、賃率差異に関しても不利差異や有利差異があるのです。この差異を賃率差異と呼んでいます。
賃率差異を算出した結果として、標準消費額よりも実際消費額の方が大きいような場合を不利差異(借方差異)と言います。具体例を挙げると、標準消費額が10,000円であるのに対して実際消費額が15,000円だったようなケースが不利差異(借方差異)となります。つまり、実際消費額の方が大きくなる、ということは(当初の予定である)標準消費額10,000円と比べると実際消費額の方が5,000円多くかかっている、ということになるのです。
この状態は、企業としては好まらざる状況とは言えません。なぜならば、思っていたよりも余計にお金がかかっている状況だからです。他の事例についても確認してみましょう。
今月の労働者(直接工)の賃金の実際消費額(なお、全額を直接作業分とする)は20,000円でした。なお、労働者(直接工)の賃金は標準賃率(@2,000円)を使用して算出しています。今月の実際直接作業時間が8時間だったと仮定します。
最初に賃金を消費した場合には、@2,000円×8時間=16,000円となるので、以下のような仕訳となります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 16,000 | 賃金・給料 | 16,000 |
考え方は、労働者(直接工)に対する賃金であり全てが直接作業分なので、直接労務費となり、仕掛品勘定となります。事例における賃金・給料の実際消費額は20,000円なので、標準消費額である16,000円よりも実際消費額の方が多額であることがわかるでしょう。
貸方の賃金・給料が16,000円ではなくて実際は20,000円だったので、これを仕訳で見てみると20,000円-16,000円=4000円少ない金額で計上してしまった、と考えます。
これを仕訳で表すと、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 賃率差異 | 4,000 | 賃金・給料 | 4,000 |
となります。
上記の仕訳を合計すれば、貸方の賃金・給料は16,000円 + 4,000 円で20,000円となるので、下表の通り、実際の消費額が反映されたことになります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 16,000 | 賃金・給料 | 20,000 |
| 賃率差異 | 4,000 | ||
仕訳なので借方と貸方にそれぞれ何らかの科目を記載する必要があります。賃金・給料という勘定は貸方にありますが、借方には何もないので「賃率差異」という勘定を用意したと考えられます。このように仕訳に際して借方に「賃率差異」という勘定が出てくることから、「借方差異」とも呼ばれています。また、会社としては賃金の支払い金額が当初の予定(設定した標準的な)金額よりも増加したので「不利差異」とも言います。
続いて、賃率差異が有利差異(貸方差異)のケースを解説します。賃率差異が有利差異となるのは、標準消費額の方が実際消費額よりも多いような場合になります。企業にとってま好ましい場合となるので、「有利差異」と言います。ここでも事例を挙げて解説します。
今月の労働者(直接工)賃金の実際消費額(全てを直接作業分とします)は10,000円でした。労働者(直接工)の賃金は標準賃率(@2,000円)を使用して計算します。今月の実際直接作業時間は8時間だったとしましょう。
前述した「不利差異(借方差異)」の事例と上記事例の相違点は実際消費額のみです。先ほどの事例では実際消費額が20,000円だったのに対して、上記事例では実際消費額が10,000円です。
したがって、前述した事例と同じく、賃金を消費した場合の仕訳は、@2,000円×8時間=16,000円となるので
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 16,000 | 賃金・給料 | 16,000 |
となります。
上記の標準消費額と実際消費額である10,000円とを比較してみましょう。この場合は、16,000円 ― 10,000 円 = 6,000円、となるので、6,000円分だけ実際にかかった金額は少なかったことになります。したがって、貸方の賃金・給料を6,000円分だけ減少させるような以下の仕訳が必要になります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 賃金・給料 | 6,000 | 賃率差異 | 6,000 |
前述した不利差異(借方差異)と異なるポイントは、仕訳をした際に差異が貸方に計上されるという部分になります。なぜ今回のケースでは借方に「賃金・給料」が出てくるのでしょうか。まず標準消費額が16,000円だったのに対して、実際は10,000円だったというわけです。
なので、賃金・給料を10,000円に修正したいということになります。しかしながら、貸方に計上した賃金・給料16,000円から直接6,000円を差し引くような仕訳方法は工業簿記のルールには存在しません。したがって、借方に賃金・給料6,000円を計上することで、貸方の賃金・給料16,000との差し引きを実施していることにするのです。
つまり、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 16,000 | 賃金・給料 | 16,000 |
| 賃金・給料 | 6,000 | 賃率差異 | 6,000 |
という仕訳を生成することになるのです。
(3)製造間接費配賦差異の仕訳手順
標準配賦額と実際配賦額との差額のことを「製造間接費配賦差異」と呼んでいます。標準配賦額とは、実際原価計算制度における予定配賦率と同様に、1作業時間あたり(操業度)いくら加工費がかかるのか、を表しているものです。
標準配賦額 < 実際配賦額、の場合をを不利差異(借方差異)と呼んでいます。例えば、標準配賦額が50,000円で実際配賦額が90,000円だとします。これは当初の予定(標準)よりも40,000円(90,000円 - 50,000円)余計にかかったということになります。
このような場合の仕訳はどのようにすればよいのでしょう。結論としては、「製造間接費配賦差異」という勘定科目を使用して仕訳処理をすることになります。事例として、以下のようなケースを考えてみましょう。
今月の製造間接費の実際発生額を9,000円とします。なお、製造間接費は標準配賦率@50円で標準配賦しているので、今月の実際操業度は100時間となっています。「標準配賦額 = 標準配賦率 × 実際操業度」なので、標準配賦額 = @50円 × 100時間 = 5,000円、となります。
この仕訳は、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 5,000 | 製造間接費 | 5,000 |
となります。
この仕訳の考え方は、製造間接費を標準配賦した場合に製造間接費5,000円で処理している、というものです。つまり、5,000円のみが製品原価となっている、ということになります。一方で、製造間接費の実際発生額は9,000円です。したがって、9,000円 - 5,000円 = 4,000円、ということで4,000円分の追加的な費用がかかったということになります。したがって、製造間接費が9,000円になるような処理が必要なので、以下のような仕訳を実施します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 製造間接費配賦差異 | 4,000 | 製造間接費 | 4,000 |
と、貸方の製造間接費が合計で9,000円になるような仕訳を生成します。そして借方には「製造間接費配賦差異」という勘定を計上することになります。
つまり、仕訳を合計すると
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 5,000 | 製造間接費 | 9,000 |
| 製造間接費配賦差異 | 4,000 | ||
という処理になるのです。したがって、製造間接費配賦差異は「標準配賦額 - 実際配賦額」で絶対に計算するようにしましょう。
こうして算出した結果がてマイナスになるようであれば、企業としては余計なコストが発生したということになる(不利差異、借方差異)ので、製造間接費配賦差異を借方に記載することが必要になるのです。
前述した不利差異のケースとは反対に、「標準配賦額 > 実際配賦額」の場合を有利差異(貸方差異)と呼んでいます。借方差異の場合は標準的な場合(当初の予定)よりもコストが多くかかってしまった場合でしたが、貸方差異(有利差異)とは、例えば、標準配賦額が5,000円だった場合に実際配賦額が4,000円だった、というような場合が当てはまります。
事例として、今月の製造間接費実際発生額が4,000円だとします。また、製造間接費は標準定配賦率@50円で標準配賦していて、今月の実際操業度は100時間だとします。この場合に製造間接費を標準配賦した際の仕訳は、@50円 × 100時間 = 5,000円なので
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 5,000 | 製造間接費 | 5,000 |
となります。
しかし、製造間接費の実際発生額は4,000円だったので、5,000円 - 4,000円 = 1,000円、つまり1,000円分だけを取り消す仕訳処理が必要となるのです。つまり、借方に製造間接費1,000円、相手方(貸方)に製造間接費配賦差異1,000円を計上する、以下のような仕訳処理をします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 製造間接費 | 1,000 | 製造間接費配賦差異 | 1,000 |
これは貸方計上した製造間接費5,000円を4,000円に減らしたいので、貸方とは反対の借方に製造間接費を1,000円計上したものです。
つまり、仕訳を合計すると
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仕掛品 | 5,000 | 製造間接費 | 5,000 |
| 製造間接費 | 1,000 | 製造間接費配賦差異 | 1,000 |
となるのです。
材料費で標準価格を使用する場合には価格差異を計算することになりました。次に労務費で標準賃率を使用する場合には賃率差異を計算することになりました。しかし、製造間接費の配賦差異は、もう少し細かくて、標準差異と操業度差異とに分けることが可能なのです。
製造間接費の差異分析は、実際原価計算における製造間接費の標準配賦の場合は予定配賦額(予定配賦率 × 実際操業度)と実際発生額とを比べて、両方の差異を予定差異と操業度差異に分析することになります。これに対して、標準原価計算においては、製造間接費の標準原価、すなわち標準配賦額(標準配賦率×標準操業度)と実際発生額とを比べて、製造間接費の標準原価差異を計算することになります。
したがって、標準原価計算においては、予算差異と操業度差異に加えて、標準操業度と実際操業度との違いから生じる差異が新たに発生することになりますが、これは「能率差異」として把握することになります。
能率差異とは、作業能率の良否を意味する差異のことであり、標準操業度と実際操業度との差に標準配賦率を乗じて算出されます。
能率差異がマイナス(標準操業度 < 実際操業度)のケースでは、作業時間が目標値(標準操業度)よりも多くかかってしまったことを意味するので不利差異になります。反対に、逆に能率差異がプラス(標準操業度 > 実際操業度)のケースでは、作業時間を目標値よりも少なく抑制することができたことを意味すすので有利差異となるのです。
3.原価差異分析の活用
 これまで説明してきた有利差異や不利差異は、原価差異分析における考え方です。製造業の現場においては原価差異を分析することが非常に重要であることを十分に理解しているものと思われますが、あまり経理に携わらない部門などにおいては原価差異分析がどのように活用されているのかよく理解されていない可能性も考えられます。そこで本稿ではベーシックな原価差異分析の活用方法について解説します。
これまで説明してきた有利差異や不利差異は、原価差異分析における考え方です。製造業の現場においては原価差異を分析することが非常に重要であることを十分に理解しているものと思われますが、あまり経理に携わらない部門などにおいては原価差異分析がどのように活用されているのかよく理解されていない可能性も考えられます。そこで本稿ではベーシックな原価差異分析の活用方法について解説します。
例えば、どうして実際原価が標準原価よりも高くなってしまったのか、ということに関して分析結果を確認したら改善策を策定することが必要になるでしょう。まず、材料費に関して、△XXXX円の不利差異が生じていたとします。どうも事実関係などを確認してみると、材料の価格が今年に入って急に値上がりしたので、予定していたよりも材料単価が高くなってしまったためとだと判明しました。この場合の改善策としては、材料単価の引き下げ要請や、より安価な購入先の取引変更、販売価格への転嫁、を検討・実施すること考えられるでしょう。
<改善策の例>
- 同じ材料を安く購入することができないかどうかを検討する。
例えば、仕入取引先や調達している国などの変更によって仕入単価を引き下げることが可能かどうか、に関して検討する。また、仕入先への値下げ交渉ができないかどうかを検討する。 - あるいは、高くなった材料費の分だけ販売価格を上げて販売先の顧客・取引先に価格を転嫁することが可能かどうか、などを検討する。
また、労務費に関しても、XXXX 円の不利差異が生じていまいた。事実関係を確認してみると、一部の労働者の作業の進捗が遅くて残業が増加したためだと判明しました。改善策としては、作業が遅い理由を把握することとその原因の解消をすること、作業手順などの標準化・自動化などを挙げることができるでしょう。
<改善策の例>
- 作業の進捗が遅い労働者にヒアリングを実施するなどして、作業が遅くなる原因を特定して、原因の解消を図るようにする。
- 作業手順(マニュアル)や工具の設置場所などを決めておき、誰であっても一定以上のスピードで作業が可能になるように、プロセスの標準化を図る。
4.(まとめ)原価差異分析を上手く活用するためには
 原価差異分析とは、原価差異の分析結果を、ビジネスにおける業務の改善などに役立てることで初めて、分析結果の有効な活用がなされたと言えるものです。それでは、分析結果を実際に業務改善や企業経営に活用するためには何が必要なのでしょうか。
原価差異分析とは、原価差異の分析結果を、ビジネスにおける業務の改善などに役立てることで初めて、分析結果の有効な活用がなされたと言えるものです。それでは、分析結果を実際に業務改善や企業経営に活用するためには何が必要なのでしょうか。
最初は、原価管理計画の策定が必要になります。そして、策定した原価管理計画に則って業務改善が実行され、検証され、そしてさらに改善計画が策定される、というPDCAサイクルをスムーズに回していくことが肝要なのです。
こうしたPDCAサイクル活動をの継続することが、生産面における無駄や非効率の低減・廃止と企業に利益がしっかりと残っていくシステムの構築へと繋がっていくのです。なぜ改善という企業活動する必要があるのか、というと、改善することによってどういった成果を得ることができるのかについて社内で共有することが可能になります。
こうした社内共有によって、改善に向けて社内全体のモチベーションも大きく向上することが期待できるものと考えられるので「改善」活動は企業にとって必要なものと言えるのです。現時点で、まだ原価差異分析を実施できていないような場合には、まず最初に「標準原価を策定する」と「実績値を正確に把握する」ということから着手してみることが宜しいのではないでしょうか。
併せて読みたい:チャットボットは職場に役立つのか?概要と仕組みを解説